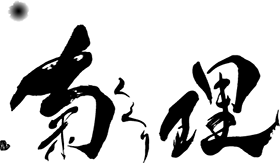『平安装束解説と着付け体験』②静岡文化芸術大学特別講義|出張雅楽演奏と平安文化講座事例
菊理のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。
菊理は
平安・天平期の宮廷装束の着付け体験
平安文化講座
解説付き雅楽コンサート
などを得意としており、大学のゼミや特別講義、平安文化講座などを全国各地で開催しています。

このたび、公立大学法人静岡文化芸術大学「文化政策学部」宮崎准教授よりのご依頼で、特別講義『シルクロード伝来の雅楽と国風文化の平安装束』を企画開催、併せて外部講師を務めました。
第2部「国風文化の平安装束解説と着付け体験」
開催日時:令和5年5月31日(水)14時30分~(1時間)
内容
第1部 「雅楽講座と生演奏の鑑賞」![]()
第2部 「国風文化の平安装束解説と着付け体験」
の二部制として実施し、この記事は第2部のご紹介となります。
(第1部の模様はこちら ![]() をご覧ください)
をご覧ください)
『平安時代の衣装着付け体験』袿・狩衣
今回の着付け体験では、授業1枠分という限られた時間内で、できるだけ多くの学生に体験させてあげたいとの先生の思いから、簡略形式として洋服の上から袿や狩衣のみを羽織る着付けを採用し、20名以上の生徒さんたちに、本物の平安装束を体験していただくことが出来ました。
 袿の着付け体験
袿の着付け体験

今回菊理が用意した鮮やかな真紅の袿と、可愛らしくきらびやかなピンクの袿は、女子学生に大人気!!
写真撮影の小道具に檜扇(ひおうぎ)と薬玉(くすだま)を用意し、これらの持ち方や、装束を着けた時の所作、作法などもお教えしました。
▷出張体験プランについてのお問い合わせはこちら→お問い合わせ

 狩衣の着付け体験
狩衣の着付け体験

狩衣は男女問わず大人気!
色違いの狩衣を、取っ替え引っ替え何回も体験する方もみえたりと、多くの学生さんに狩衣装束を楽しんで頂きました。
▷出張体験プランについてのお問い合わせはこちら→お問い合わせ

『装束の解説』
 「狩衣」名前の由来と構造解説
「狩衣」名前の由来と構造解説

狩衣は平安時代の男性貴族のカジュアルファッション。そもそも、なぜ『狩衣』と名付けられたのか? 名前の由来となった、この衣装の構造を実演解説しました。
▷出張体験プランについてのお問い合わせはこちら→お問い合わせ
 「時代による装束の変化」実演解説
「時代による装束の変化」実演解説

生徒さんにご用意した平安装束は今から千年前の平安時代の貴族のものですが、今回の特別講義ご担当の宮崎准教授はご専門がシルクロードとのことで、特別に奈良時代の装束「天平装束」もご用意させていただき、シルクロード由来の天平装束を着装しました。
「天平装束」とは、中国(唐)の衣装を取り入れて8世紀頃花開いた日本の伝統装束です。

宮崎先生と仲の良い同僚の先生が見学にお越しになりましたので、せっかくならと、急きょ平安装束「袿」を着装させていただきました。

お二人の先生がそれぞれ天平装束と平安装束を着て並ばれたところで、時代による服飾文化の特徴を解説しました。
天平装束は現在の洋服のように袖がタイトで、ショールのような布をまといます。まるで乙姫様のようですね。
平安装束は袖が大きく広く、全体に布もたっぷり使っています。
古代の女性は衣服から「手」を出すことを恥ずかしいこととしていました。
また、当時貴重品であった生地(布:織物)をふんだんに使った衣服は「権威の象徴」と考えられていたことから、奈良時代から平安時代へ時代が下るにつれ、貴族の装束は大きくゆったりとしたものに変化していったことを、実演を交えながら解説させていただきました。
生徒さんからは
「歴史や古典の教科書で見たことあるけど、実物を見て”なるほど~!”と思った」
「実際に着てみて日本の文化の素晴らしさを体感できた」
と嬉しいお声をいただきました。
リクエスト「空蝉(うつせみ)」実演解説

会場から「空蝉(うつせみ)」の質問とリクエストを受け、空蝉を急きょ実演と解説をしました。
「空蝉」とは、源氏物語で光源氏との逢瀬を拒んだ女性として描かれています。光源氏が部屋に忍び込んだ時、衣を残してするりと逃げてしまった姿が「蝉の抜け殻」のようだったことに由来します。

本来は裳を着けた十二単(五衣唐衣裳)で表現しますが、今回は時間と装束の都合で簡略版としました。文献でしか知らなかった空蝉の過程を間近で見、雰囲気を感じていただけたようで、先生も生徒さんも熱心に撮影やメモを取られていました。
生徒さんから、この日の感想をたくさんいただきましたので次回の記事 でご紹介いたします。
▷出張体験プランについてのお問い合わせはこちら→お問い合わせ
衣裳紹介(第2部)
<今回の着付け体験でご用意した衣装>

・赤色地に三色向蝶文の袿
(あかいろじにさんしょくむかいちょうもんのうちぎ)

・薄桃色地に三色浮線菊文
(うすももいろじにさんしょくふせんぎくもんのうちぎ)

・天平装束一式
(てんぴょうしょうぞくいっしき)

・緑色地に雲鶴文の狩衣
(みどりいろじにうんかくもんのかりぎぬ)

・山吹色地に雲鶴文の狩衣
(やまぶきいろじにうんかくもんのかりぎぬ)
※上記装束「袿」「狩衣」などは販売もしておりますので、お気軽にこちら ![]() へお問い合わせください。
へお問い合わせください。
(この記事でご紹介している装束について、色や柄が廃版となっている場合もございます。)
当日概要(第2部)
>>第1部「雅楽演奏鑑賞 ![]() 」、「演奏動画
」、「演奏動画 ![]() 」もぜひご覧ください。
」もぜひご覧ください。
今回ご依頼をくださった宮崎准教授は、国立大学岐阜大学日本語・日本文化教育センターで開催した「留学生向け十二単着付け体験と雅楽ワークショップ」が大好評であったことを、岐阜大学関係者の方から聞いてくださったとの事。
ぜひご自身のゼミの生徒たちにも、装束体験をさせてあげられないかと菊理に連絡をくださり、今回の特別講義となりました。
宮崎准教授のゼミは「文明観光学」で、先生ご自身もシルクロードを研究テーマとされてみえることから、雅楽の歴史的背景やシルクロード伝来の雅楽器の解説からスタートし、今回最大のご希望であった、生徒さんたちの装束着付け体験と、短い時間ではありましたが、盛りだくさんの内容で、生徒さんたちにも大好評を得、ご依頼くださった宮崎先生からも、喜びの声と共に感謝のお言葉を頂きました。
菊理の「出張体験プラン」は本物の日本文化がお手軽に体験でき、学校や博物館、外国人観光客への歓迎プログラム、ホテルや旅館、企業様のアトラクションとしてもおすすめです
体験プランは全国に出張可能です。
イベント企画会社、旅行代理店、自治体や企業、団体の企画担当者様など、ぜひお気軽にお問い合わせ ![]() ください
ください
菊理は多くのイベントや歓迎レセプション、学校公演に長年携わり
実績、経験が豊富です
本物の有職装束やしつらえを体験できる
解説付きワークショップ講座、雅楽や服飾文化にまつわるセミナーを
ステージイベントだけでなく配信などにも
幅広く対応致します。
全国どこへでも出張し感動と迫力をお届けします
どうぞ、お気軽にお問い合わせください。
雅楽二重奏「菊理」
文化庁「文化芸術による子供育成総合事業」協力芸術家
0532-34-7150
090-2577-0958(担当:近藤)